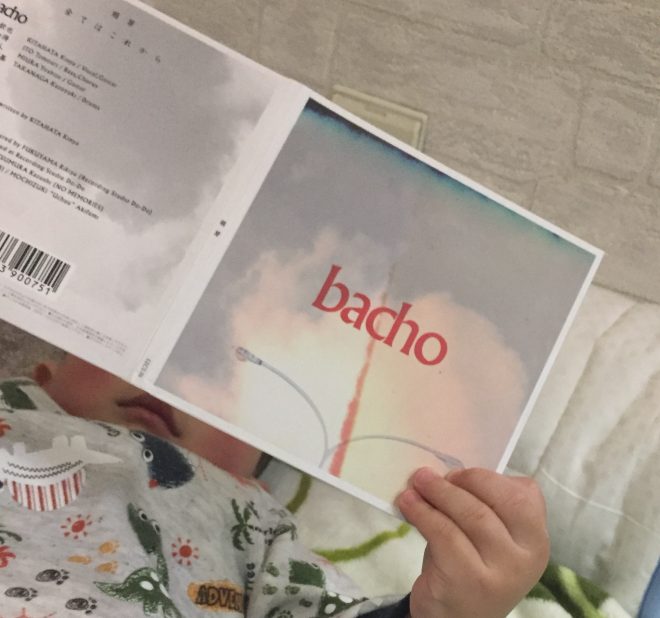
先日、嬉しい知らせが飛び込んで、でも、今後に不安を抱き、自己嫌悪にさいなまれながら、でも、これまで一緒にもがいてくれたゼミ生の頑張りも一緒に評価されたものだと思い、ちゃんと記してまとめよう。
もう6年前かなぁ。初代は、ゆかさん(旧姓:久保田さん)や菊池さんが取り組んだ脳波(事象関連電位)の研究。専門家の荒生先生に弟子入りして、測定方法などを教えてもらい、マニュアルしっかり作って後輩にバトンをタッチしてくれた。その後は男筋の”たてつな”(縦の人間関係のつながり:先輩後輩)を紡いできたのが脳波研究だった。
翌年からゼミ1期のおかみ(神永君)、2期ジュニア(中澤君)、3期ひめ(姫野君)、4期コバ(小林君)の男性版たてつな。それぞれ先輩の卒論を参考にして負けじと卒論を執筆してくれた。そして卒業後もOBとして大学に遊びに来てくれたり合宿に来て後輩をフォローしてくれたりしてくれた。そのほかにも、あさみちゃん(佐藤さん)、レイ君(小竹君)、春ちゃん(森谷さん)たちが一緒に脳波研究をして卒業していった。私は脳波の専門家でもないので、ゼミ生たちと一緒に試行錯誤しながら積み上げてきた研究である。
大学院生がいない、ごく普通の大学において、表情模倣の研究だけでなく、もう一つの系統として脳波研究を継続的に実施できたのは、同級生との切磋琢磨や、先輩後輩の関係の大切さを理解してくれた学生たちがいたからだと心から思う。
本題に入ると、先日、科学研究費の挑戦的研究(萌芽)の採択通知が届いた。
事象関連電位を用いた研究の内容である。てっきり4月発表と思っていたので、不採択になったと思っていた。去年も萌芽に出して、不採択だったので二年連続の不採択に自分の研究力の低下や自身の研究能力の枯渇を恥じたりもし始めていた。ただ、今もなお、研究の最前線で活躍する後輩などを見ると、論文もかけない自分に嫌悪する日々でもある。もっとアウトプットを意識して、論文書くことにまい進しないといけないけど…
私を指導教員として選んでくれて、一緒に苦悩の道を模索してくれたゼミ生がいたから、楽しく研究できていると心から思う。そういった意味では、私は恵まれた教員であると心から思う。ゼミ生全員がそういう道を選ぶのでなく、本気で取り組みたいと思うゼミ生と一緒に取り組んできたというほうが正しい。同期との切磋琢磨や先輩後輩とのたてつな。このことが大切だと共有できる人たちと。
ただし、今後は不安な部分も多い。仕事の状況も家庭の状況も変化しつつあって、若かりし頃より、教育というか研究というか、学生と実験したりスタッフのことをしたりする時間が年々減ってきて…その基盤に無駄話をしながら関係性を構築していくという私なりの方法も、やはり時間の制限を受けてきたからだ。
だけど、いつものように、同じようにゼミ生に愚痴をこぼしながらも、『萌芽』を信じて、『全てはこれからさ』と前向きに向き合っていきたい。
前回(4年前)、挑戦的研究の採択を受けたテーマは、初年次教育のSAや表情模倣の研究のことで、ここでも多くの学生が頑張ってきてくれたから実現したテーマだ。来年から、その集大成としてカリキュラムに落とし込むところまで進んだ。
このように、私は今の大学で、一生懸命一緒にもがいてくれる学生と出会い続けている。それは私がすごいからではない。一緒に”たてつな”を共有してくれた学生との共同作業だと思う。
論文がかけず、自己嫌悪に苛まれて苦しい時間ばかりだけど、bachoの音楽に支えてもらいながら、私のペースで各駅で進めばいい。
「これでいいのだ、これでよかったんだ ようやく来た乗り込む電車、各駅で進む」(『これでいいのだ』より)